児童書と一言でいっても、対象者の年齢は赤ちゃんから12歳頃までと幅広く、その種類は多岐にわたります。
図書館において児童書を排架するに当たっては、資料の特性や大きさなどに応じて専用の書架を用意することが必要です。
専用の書架の例としては、比較的小さなものが多い赤ちゃん絵本のための書架や、紙芝居架、読み聞かせ用の大型絵本の書架などが挙げられます。
また、各資料の主な利用者の年齢層に配慮した上で、展示と収納の両面から考えて排架することが求められます。
特に絵本は、子どもに絵本の表紙を見せ絵本の魅力をアピールするという展示の観点も十分考慮して、一部平置きにするなどの検討が必要です。
図書館によっては、絵本を物語、知識絵本、郷土絵本など細分化して排架する事例もみられます。
このように、児童書が豊富な図書館においては形態的な種類での区分だけでなく、内容的な種類での区分を併用することも、アクセシビリティを高める効果的な方法といえるでしょう。
いずれにしろ、子どもの利用しやすさを最優先として排架の方法を熟慮すべきであると考えます。
僕が仮に児童書の新刊本を排架する担当者である場合、例えば絵本、紙芝居、漫画などはそれぞれまとめて排架し、必要なコレクションに容易にアクセスできるようにします。
また、幼年文学や低学年向きの図書は、同じ児童書の書架のなかでも低い位置に別置し、身長が低くても目に入りやすく、手も届くようにします。
排架を低くすることで、子どもは大人に頼ることなく自力で難なく読みたい本を見つけ出すことが可能となるでしょう。
そのような成功体験を積み重ねることによって、子どもは自ら率先して行動しようとする意欲が高まり、主体性の向上も期待できます。
排架そのものの工夫と合わせて、児童コーナーの場所を示す書架マップやサインも作成します。
その際、極力漢字を減らしたり、マップ内で目印を絵で表したりするなど子どもが理解しやすいものを作成し、掲示場所もより子どもの目に入る位置となるよう配慮します。
館内OPACも一般用とは別に児童用を設置し、設置台の高さも子どもにとってちょうどよい高さにします。
また、OPACの利用方法が分からない子どもにはこちらから優しく声かけし、丁寧な指導を心がけます。
このような排架及びそれに関連する取組を通して、利用する子どもが図書館を居心地の良い場所と感じてくれれば、生涯にわたる図書館利用及び読書習慣の定着につながっていくと思います。
まとめ
児童書の配架(排架)に関して考えてみました。
「はいか」には2通り漢字がありますが、僕は「排架」に統一して記述してみました。
こちらの本を参考にしています👇
“自分が子どもだったらどんな風に排架されていると嬉しいかな”ということを考えながらまとめてみました。
“知らない大人に声をかけづらい”という子どもの気持ちを念頭に置き、以下に子どもだけで自己完結できるかという視点が重要だと思います。

子どもたちに利用してもらうために、大人以上に細やかな配慮が必要なんだね

ウサギの子ども向けに暗くて狭い穴にも排架してほしいな!


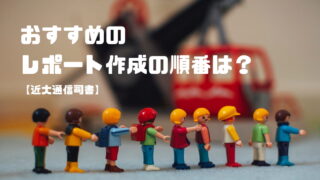
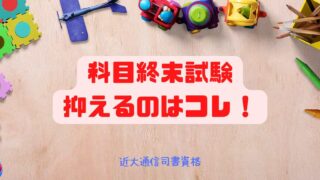

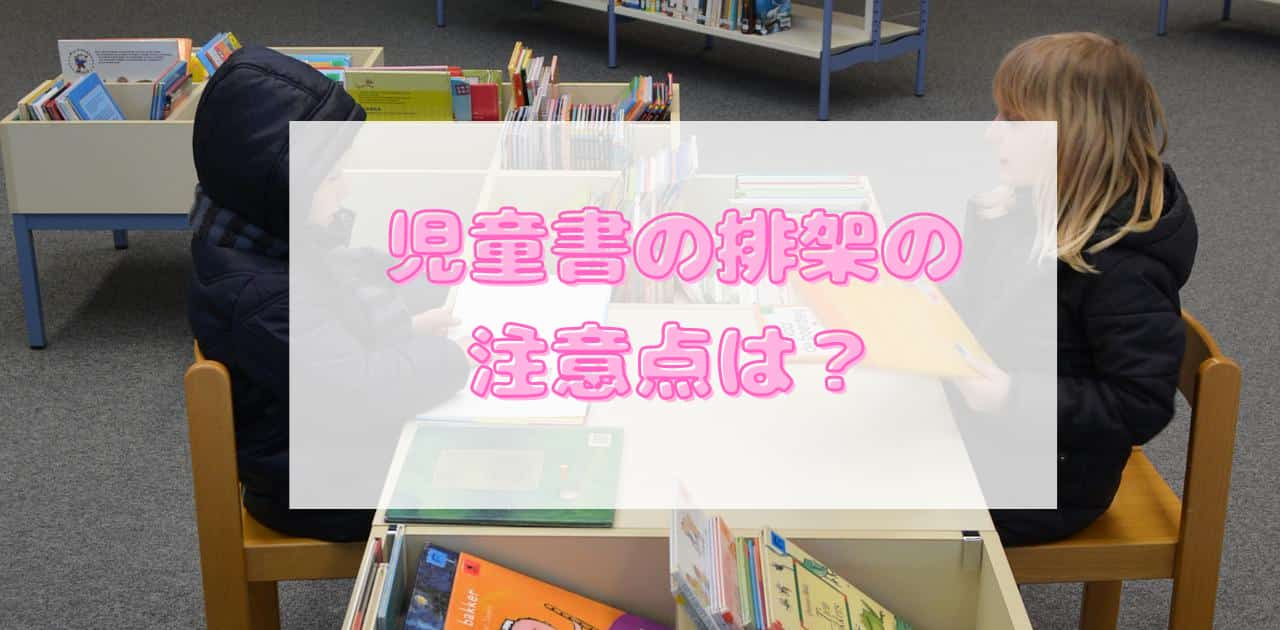






コメント