読み聞かせとはどんな活動か
読み聞かせとは、声に出して本を子どもに読んであげる活動です。
読み聞かせは、子どもに本の面白さを体験してもらい、本への興味を育み、読書をする素地をつくることのできる効果的な方法です。
また、読み聞かせには、文学を耳で楽しむこと、その楽しみを人と分かちあう喜びなど一人で黙々と楽しむ読書とは違った魅力があります。
さらに、語り手も子どもたちの反応を通して楽しみや充実感が得られるため、大変有意義な活動といえます。
読み聞かせを行うに当たっては、次のような点に配慮すべきでしょう。
1 本の選び方
読み聞かせでは絵本が多く利用される。どのような絵本を選ぶか心を配る必要があります。
最初に、聞き手の年齢に合わせて選書をするということが基本です。
そのため、読み聞かせの実施の際には、ある程度発達段階に分けて実施することが望ましいです。
次に、本の大きさと絵の種類に留意する必要があります。
複数の子どもが参加する場合、会場の後ろからでも絵が見て取れる本を用いることが望ましいです。
事前に本を離れたところから見て、見え方を確認しておく必要があります。
最後に、絵と文が一致しているか、バランスはよいかということに気を配る必要があります。
絵と文が一致していなかったり、バランスが悪く一場面の絵に対して文章の分量が多いと、子どもは語り手の言葉と違う絵を長々と見せられることになり、イメージを膨らますことができなくなります。
2 読み方
語り手は、読み聞かせを行う本をあらかじめよく下読みしておくことが大切です。
話全体の構成や流れを把握しておくことで、タイミングよくページをめくることができます。
読み方は、リズム、間、テンポに気を付けながら読むことが重要です。
下読みの段階で実際に声に出して読む練習をすることで、これらの技術をブラッシュアップできるでしょう。
十分に練習を積んでおけば、当日は子どもの反応を見ながら余裕をもって読むことができます。
また、大げさな感情移入はせず、自然体で心を込めて丁寧に読むことを心がける必要があります。
そのほか、本がぐらぐらしないよう安定した持ち方をし、読む前に全員がしっかりと絵が見えているか確認して始めることが重要です。
読み終えたら、子どもたちからの質問や呼びかけに十分に応えてあげることで満足度が高まり、「読み聞かせは楽しい」「また参加したい」という気持ちを醸成することができるでしょう。
読み聞かせに向く絵本
ここでは、読み聞かせに向く絵本として「おいもころころ』(いもとようこ文・絵、金の星社、2018)を紹介します。
この本は、昔話を題材として書かれた大変愉快なお話です。
和尚さんに「なんでもわしのするとおりにやるんじゃ」と言われ、素直にありとあらゆることを真似してしまう小僧さんたちの姿に思わず笑みがこぼれてしまいます。
文は「ころころころ」「ドテーンドテーンドテーン」など、リズミカルな言葉の繰り返しが心地よく、耳に入りやすいです。
絵も登場人物の表情が活き活きと描かれ親しみやすく、少し離れた場所からも視認性が高い作品です。
この本の読み聞かせを行う際の対象年齢は、幼児から小学校低学年までが適当でしょう。
目的は、読み聞かせを通して本の面白さを知り、読書をする素地を形成することです。
また、「次にどのようなしぐさを小僧さんたちは真似するのか」という想像力の刺激もねらいです。
さらに、この本を一緒に楽しむ子ども同士の連帯感を生む効果も期待できます。
以下、この本を使った読み聞かせの手順を述べます。
1 練習
まず準備として、語り手は本をあらかじめよく下読みしておくことが大切です。
話全体の構成や流れを把握しておくことで、タイミングよくページをめくることができます。
十分に練習を積んでおけば、当日は子どもの反応を見ながら余裕をもって読むことができます。
2 読み聞かせする本の特徴を事前周知
『おいもころころ』が滑稽で笑える本であることを事前に知らせておくことで、子どもたちの期待感を高めることができます。
3 本番
本番は、リズム、間、テンポに気を付けながら読むことが重要です。
特にこの本は笑い話であるため、子どもたちから最も大きな笑いが引き出せるよう、最適な間をうまく取りつつ読み進めることが重要です。
各場面での声の強弱もポイントとなる。下読みの段階で実際に声に出して読む練習をしておくことで、当日ブラッシュアップされた技術を披露できるでしょう。
4 終了後の配慮
読み終えたら、子どもたちからの呼びかけに十分に応えてあげることで満足度が高まり、「読み聞かせは楽しい」「また参加したい」という気持ちを醸成することができると思います。
課題として、この本に影響された子どもたちが、いたずらで特定の子の真似をし続けて困らせてしまうことが考えられます。
それを防ぐために、おわりに一言「和尚さんのように相手が真似されて困っていたら、その人の真似をするのはやめようね」と添えるとよいでしょう。
まとめ
具体例は図書館で何冊か見比べながら、良さそうな本を紹介してみました。
「簡単に見つかるだろう」と高をくくっていたのですが、細部まで丁寧に描かれた絵の本が多く、逆に細かい描写が少なく遠くからでも見やすい絵本を探すのは思ったより難しかったです。
絵本の選び方一つとっても、司書の仕事は利用者があまり意識していないところまで気配りがなされていることに気付かされました。

読み聞かせする本は自分自身が楽しいと思える本を選ぶのがよさそうだね!

『おいもころころ』、ベタですがシンプルに笑えます😊


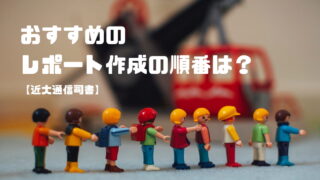
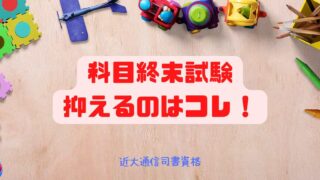

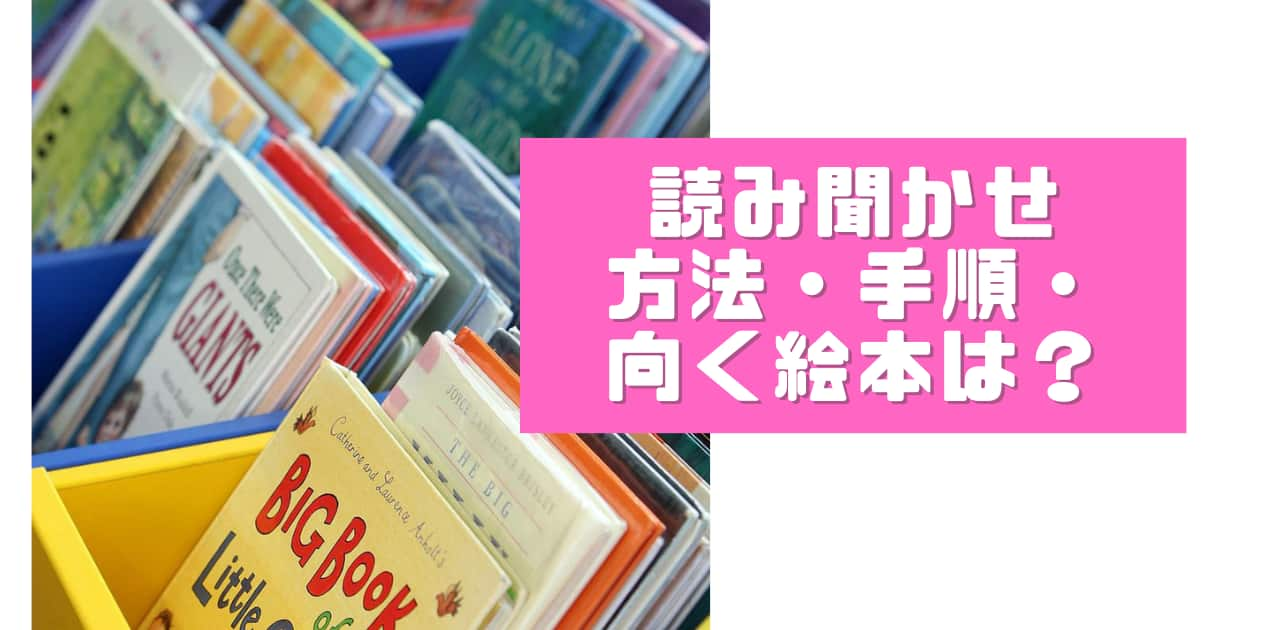

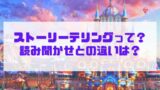



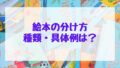
コメント